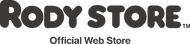馬(ロディ)がつなぐ心と身体
~実際の乗馬体験で感じた馬の魅力~

今回は、神奈川県にある相模原麻溝公園ふれあい動物広場を訪れました。
日本Gボール協会の役員でもあり、この動物広場の管理運営をしている公益財団法人ハーモニィセンターの鈴木真さん(施設長)にお話をお伺いしました。

鈴木さんは少年時代から、ハーモニィセンター主催のキッズCAMPに参加され、長年馬と関わってこられました。現在は麻溝公園ふれあい動物広場で、馬を中心としたさまざまな動物とのふれあいや、障がいがある方への乗馬教室、また馬の世話を通して子どもたちのこころの成長を助けるポニー教室など、幅広いお仕事をされています。
公益財団法人ハーモニィセンターは障がい者乗馬を日本で最初にスタートさせた団体と言われていますが、そのための研修を受けたり、施設を準備したりして、受け入れ態勢が整ってからということではなかったらしく、「本人が乗りたいって言っているから乗せてみよう」という、乗る人も乗せる側もまさに誰もがまったく初めてのチャレンジだったとお話しくださいました。
お互いが勇気をもってチャレンジしたことで、こんな知識が必要だねということがだんだん分かっていき、障がい者乗馬の色々な側面を学びつつ、現在に至っているとのことでした。
誰よりも馬の魅力、そして馬に乗ることの素晴らしさを知っている鈴木さん。
ロディのモチーフは馬。ということで、来年2026年は午年ということもあり、今回は『馬』の魅力をたくさんお伝えしたいと思います。
心と体、社会性を育む馬との時間

相模原のこちらの公園には、13頭のポニーを筆頭に、様々な動物がいますので、一般の子どもさんを対象にした乗馬体験だけでなく、さまざまな動物とのふれあい体験を行うことができます。
また障がいがある方の乗馬をメインとした乗馬教室の開催や、馬小屋(馬房)の掃除や馬のえさやり、馬の餌作りなども含めてだいたい1時間くらいのポニー教室、親子2人乗りの乗馬体験、大人向けの健康づくりのための乗馬教室などを年間を通してさまざまなプログラムも並行して行っています。

さらに、小学校1年生から馬のお世話をしたいとう子どもたちは、ボランティアとして学期中の土日祝日や夏休み中にサポートするために通ってくれています。馬とふれあい、馬と関わることでの心や体、社会性なども育まれます。
怖さを克服し、喜びを味わおう

この動物広場にいる馬のすべてはポニーです。ポニーというのは体高(地面から首と背中の境目の高さ)が147cm以下の馬の総称のことで、実はかなり大きいサイズの馬もいるので、最初はとっても怖さを感じる子どもさんもいます。
もちろんこの公園で実際に体験できる乗馬はレクリエーションなので、楽しさや喜びを感じられることが第一と思っています。それにプラスして子どもの時期に馬とふれあってほしいと思う大きな理由の1つとして、意思のある体の大きな生き物と対峙し、ふれあうことで、怖さや緊張を克服するということがあります。
馬に触れることや、自分の力で馬に乗ることによって自信が生まれ、達成感やできる喜びを感じてもらうことが大きな目的です。
また障がいがある方の場合は特に、その場の雰囲気や空気感にとても敏感で、楽しい、怖いなど、どのように感じているかはその方のリアクションを見ているととてもよく分かります。
なので、できるだけ楽しい雰囲気を作りながら乗馬に取り組んでもらうように心がけています。
その雰囲気づくりに役立つのがロディと同じような形の、ピーナッツ型のバランスボールです。プレ運動としてピーナッツボールに乗ってもらい、心と身体のウォーミングアップをしてから実際に乗馬をしてもらいます。

イタリアの老舗 バランスボールメーカー レードラプラスティック社製
脳性まひなど、下肢に障害がある方は、筋肉や関節の可動性に制限があり、股関節(股)を大きく開くことが難しい場合があります。そんなときピーナッツボールに座ってバウンディングを行うことで、自然と股関節まわりの緊張が取れて、固く緊張していた体がほぐれたり、リズミカルに弾む運動の心地よさが怖さを和らげてくれて、心までほぐしてくれるという効果もあります。
ほんものの馬(ポニー)に乗る前に、プレ運動をしておくことで、怖さや緊張が少しでも薄れていればと思います。
ボールやロディが、乗馬体験をさらに効果的に
そして馬に乗るということは特別な瞬間ですが、ボールやロディに乗ることはいつでも、どこでも、たとえば自宅に居ながらでもできてしまいます。
特に障がいがある方が乗馬をすることができるのは、だいたい10分から20分が限度。その短い時間のなかでより効果を出すためには、ピーナッツボールやロディを日常的に使って体を慣らしておくことで、実際の乗馬の身体の使い方にスムーズにつなげていくことが重要です。
何より、リハビリ訓練のような必要に迫られる感覚ではなく、楽しみながら遊び感覚でできて、さらに実際の乗馬にも良い効果があるという、たくさんのメリットがあることがいいですね。
『本人だけではなく、保護者の方も喜んでくれることを大切にしています。』

「ダイバーシティ」や「インクルーシブ」という言葉が浸透してきている現代ではありますが、障がいがある方が気軽に様々なことを体験したり、時には思い切ってチャレンジしたりするということには、まだまだハードルの高さを感じる現実もあるようです。
そんなときに障がいがあるお子さんが乗馬を通して、1人でもバランスを保ちながら乗れている姿や、前回よりも何か1つでもレベルアップした乗馬の動きができるようになった姿を見ることができれば、親御さんやまわりの人にとっても自信や喜びを感じることができるのではないかと思っています。
乗馬をしている本人が自信を持つこともとても大きなことですが、周りの人にとっても自信になるということも大きな意味があると考えています。なので本人だけではなく、保護者の方が喜んでくれるということも同じようにとても大切にしています。
日々の生活の中では「できない」こともあるかもしれませんが、「できる」ことが1つでも増えていくことが本人、そして保護者のみなさんの自信にもなっていきます。そしてそれは障がいがある、ないに関わらず誰にとっても同じことですよね。子育ての中でも、子どもたちの「できる」が積み上がって成長を感じられると、親御さんはとっても嬉しく感じるのではないでしょうか?
馬の体温を感じてほしい

馬の体温は何℃くらいあるかご存知ですか? 一般におよそ37~38℃と言われていて、人間の体温より少し高いので、人が座る部分に鞍(くら)を付けずに馬にまたがってみると、その暖かさを実際に肌で感じることができます。
とくに障がいがある方は、体、特に筋肉を動かすことが少ない分、動かせていない部分の末梢の血流が少なくなり体温自体も低くなってしまう傾向があります。ですので、あえて鞍を付けずに乗ることで、馬の体温の温かさを実際に感じ、同じ生き物であることのぬくもりを知ったり、またご本人の血行が良くなったりという効果もあるようです。

意外な事実、乗馬と歩行の運動量の差は!?

馬に乗っているときの運動量と人が歩いているときの運動量が実は同じくらいと知っていましたか?
たとえば人間は歩く際、右脚と左脚を交互に入れ替えながら歩きます。その際、骨盤自体もわずか左右交互に動き、片脚で自分の体重を支えているときはバランスを保つために反対側の体幹の筋肉を無意識に働かせています。この骨盤の動きや姿勢保持の動きは、乗馬も同じように発揮されます。
骨盤の動きに集中して乗ってみました!!
実際に、ロディスタッフがポニーに乗せてもらいました。
鞍(くら)を外すことで、鞍を着けていると気付けないことをたくさん感じることができます。 さきほどの歩行動作の際の骨盤の動きや体幹の筋肉の働きとまったく同じような動きを、鞍を外して馬にまたがり、ゆっくりのスピードで歩く常歩(なみあし)をしてみると、はっきりと感じることができました。
つまり、馬に乗ることそのものが実際は歩行動作と同じ体の使い方になって、とてもいい運動になるというわけです。 鞍を着けていてもその動きを感じとるために、目を瞑って馬に乗ってみました。
すると自分の体や馬の動きに意識を向けやすくなり、結果として自分の体の動きや、骨盤の動きを感じとることができました。

そして少し早いスピードの速歩(はやあし)の乗り方では自然に体が上下に動きはじめます。 実はこの縦方向の揺れ、普段の日常生活で実際に体験しようと思っても、なかなか同じような状況は作れないですよね。 でも、バランスボールやロディで『弾む』動きはこの縦に揺れる動きととてもよく似ています。
そして、この『弾む』動きは姿勢、特に脊柱のアライメントをより自然な状態に調整してくれる効果があります。 乗馬姿勢が美しく、格好良く見えるのは、この縦揺れの動きの結果かもしれませんね。 もし普段の姿勢で背中の丸まりが気になる方には、乗馬やロディでのバウンディングをぜひオススメしたいです。
障がいがあると生活の中での動きのバリエーションは限られてしまいがちですが、馬に乗るということは、いつもとは違う態勢や姿勢をとることができるので、新しい動きの経験や感覚を少しでも感じてもらえたらと思います。
特に、からだが完成する大人になってからスタートするよりも、成長期でからだが柔軟に変化する子どもの頃からスタートするほうが効果的ですし、乗馬の際の補助者が十分にサポートすることができるので、安全面から考えてみてもオススメです。”乗馬をしたい”という気持ちがいつの間にか”外出したい””チャレンジしてみたい”というモチベーションになって、少しずつでも子どもたち自身の世界を拡げて行ってほしいと思います。
上手な転び方の練習にも
障がいがあるお子さんだけではなく、最近は転び方がわからない、転んだときに上手に手が出ない子どもさんがたくさんいるという話を聞きます。 乗馬をすることで姿勢を保つ体の使い方を身につけることができますし、乗馬ができないときも、自宅や児童センターなどでロディで遊びながらバランス感覚を養って、色々なスポーツや運動、遊びにチャレンジしてもらいたいです。
オススメしたい『ポニーキャンプ』
公益財団法人ハーモニィセンターでは、メインの活動のひとつとして、子どもたちのCAMPを実施しています。 日本全国から子どもたちが集まり、集団生活をしながら川遊びなどの野外活動が体験できますが、ポニーCAMPでは馬のお世話をしたり、馬の乗り方を覚えたり、馬のお世話をメインにした、得がたい経験ができるCAMPです。 本当に馬ファーストのCAMPですよ。詳しくは こちらをチェックしてみてくださいね。


公益財団法人ハーモニィセンター
https://harmonycenter.or.jp/about/
(今回取材をした動物広場)
相模原麻溝公園ふれあい動物広場
住所:神奈川県相模原市南区麻溝台2317-1
電話:電話:042-778-3900
メール:sagamihara@harmonycenter.or.jp
ふれあい動物広場のホームページはこちら
https://asamizo-animal-square.com/
2026年は午年(うまどし)。
馬を通して、ロディを通して、子どもたちの心や体の成長を助けることができますように…!!
これからの未来を生きる子どもたちへ、障がいを持った方もそうでない方も、みんなが一緒に新しいものに挑戦し続けることができますように!!
大人はその環境を整えていきたいですね。